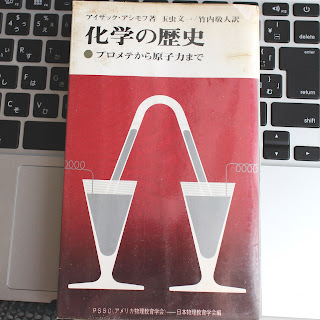体調が悪くて、しばらく外出を控えていたが、昨夜は昔の若者3名でカラオケにいき、2時間ほど唄ってきた。一人あたり10曲くらいか。先にアルコールを服用しているので、それぞれ上手く唄っていると美しい誤解をしながら楽しく大声を出してきた。
3人が交互に選ぶ曲は、ランダムのようだが、だんだんその場の流れができ、ある種の関連性を持ったものが選ばれていく。連句というのは自らやったことがないが、先人の連句集を覗いてみると、どうもこのカラオケの曲の選ばれ方に似た感じがする。阿吽の呼吸、付かず離れず、空気を読みながら選んでいく。陽気な歌のあとに、ものがなしい歌を選んだり、同じ時代の歌を選んだり、主題が似た歌を続けたり。これらの連想の発想のパターンを整理すると役に立つかもしれません。
人間が自分の頭で考えて行動する場合、この連想力は大きな力を発揮していそうである。連想力に乏しければ、次の行動のヒントが限られ、つまらない行動パターンに陥らないともかぎらない。他とのコミュニケーションにも連想力は重要であろう。貧困な応答はコミュニケーションを断ち切ってしまう。
「カラオケで学ぶコミュニケーションの基礎」というテキストがあってもいい。
昨日、原子仮説の嚆矢は、寺田寅彦先生が紹介したルクレチウス、と書いた。カラオケの前に書店に立ち寄って、理学関係の本を立ち読みしたら、ルクレチウス以前にもっと大切な人がいるのを忘れていたのに気づいた。
ギリシャ哲学史などでは、レウキッポスやデモクリトスが原子説を唱えたとある。アトモスという言葉はデモクリトスが使った。アトムの語源である。後にエピクロスが受け継ぎ、詩人ルクレティウスが「事物の本性について」で紹介した。彼らの書き残したものはほとんど失われたが、「事物の本性について」は残ったので、我々はこれにより、ギリシャ人たちの原子論を知ることができる。
(この記述はアシモフ先生の『化学の歴史』1967年、河出書房、によっています。いまはちくま学芸文庫で出ているらしい。高校生や大学一年生にはピッタリの本だと思ってます。)
寺田寅彦先生とともにエライと私が思っている、ファイマン先生は『ファインマン物理学』(1967年、岩波書店。英語ならオンラインでただで読めます。)の冒頭に次のように書きました。いちばん大事な知識は物質がすべてある種の性質を持った原子から成り立っている、ということだ。なるほど、と私は思い、それだけは覚えました(^O^)
さて、このあと、連句の本も発掘しよう(^O^)
2016年11月29日火曜日
2016年11月28日月曜日
ルクレチウスと、ラウエと、興味の対象ははてしなく増える
寺田寅彦先生の「ルクレチウスと科学」を斜め読みする。ここでは原子論(物質の基本単位は原子。寺田は現代の原子と区別するため元子と表記している)の、嚆矢としてのルクレチウスを紹介するとともに、広く自然哲学者としてのルクレチウスを紹介している。
途中に「しかし無限の空虚の中にいかにしてある「中心」が存在し、かつ支持されうるかという論難は、ニウトン以前の当時の学者には答えられなかったであろうのみならず、現在においても実は決して徹底的には明瞭に答え難いものである。」という一句がある。(iBooks版、寺田寅彦全集)
この文章が発表されたのは昭和4年(1929年)であるらしいから、ハッブルが島宇宙の光の赤方偏移から、宇宙の大きさとその拡大を唱える以前に書かれた。寺田寅彦はこのへんの論争をもちろん知っていたので、「徹底的には明瞭に答え難い」と表現したのだと思う。
ルクレチウスの言説は自然一般に渡っているが、寺田寅彦は現在の学者の専門に閉じこもりがちな傾向をやんわりと批判しようとして、この随筆を描いたと思われる。
このあたりのことを、科学論文ではどう書いているか知りたい。寺田寅彦全集科学編を買うのもいいが、高いのでまずは現物を見てから。とりあえずは、インターネットで論文をあさる。
寺田寅彦先生がベルリンでであったはずの、X線回折のラウエ先生。実際の生涯のことは知らなかったが、少しだけググってみたら、波乱万丈(もちろんナチスへの反抗)であることに驚いた。これも調べてみます。うーん。ドイツ語をもっとしっかりやっておけばよかったなあ。ドイツ語通訳をやっている友人に相談しようかしら。
途中に「しかし無限の空虚の中にいかにしてある「中心」が存在し、かつ支持されうるかという論難は、ニウトン以前の当時の学者には答えられなかったであろうのみならず、現在においても実は決して徹底的には明瞭に答え難いものである。」という一句がある。(iBooks版、寺田寅彦全集)
この文章が発表されたのは昭和4年(1929年)であるらしいから、ハッブルが島宇宙の光の赤方偏移から、宇宙の大きさとその拡大を唱える以前に書かれた。寺田寅彦はこのへんの論争をもちろん知っていたので、「徹底的には明瞭に答え難い」と表現したのだと思う。
ルクレチウスの言説は自然一般に渡っているが、寺田寅彦は現在の学者の専門に閉じこもりがちな傾向をやんわりと批判しようとして、この随筆を描いたと思われる。
このあたりのことを、科学論文ではどう書いているか知りたい。寺田寅彦全集科学編を買うのもいいが、高いのでまずは現物を見てから。とりあえずは、インターネットで論文をあさる。
寺田寅彦先生がベルリンでであったはずの、X線回折のラウエ先生。実際の生涯のことは知らなかったが、少しだけググってみたら、波乱万丈(もちろんナチスへの反抗)であることに驚いた。これも調べてみます。うーん。ドイツ語をもっとしっかりやっておけばよかったなあ。ドイツ語通訳をやっている友人に相談しようかしら。
登録:
投稿 (Atom)