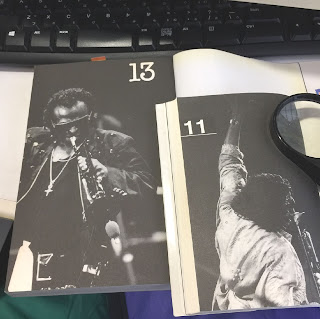マイルスの自叙伝を読んで、感じたのは、同時期の(ただし一方は早死=事故死だったが)トランペッターなのに、クリフォード・ブラウンと性格がまるで違うなということだった。
そこで、昔買ったクリフォード・ブラウンの伝記を捜してきた。少し拾い読みして違いの原因を探りたい。
『クリフォード・ブラウン 天才トランペッターの生涯』(ニック・カタラーノ著 川嶋文丸訳 2003年 音楽之友社)。
ファンの片割れなので、発行時にすぐ買って読んでいる。しかし今回のマイルスの自叙伝ほど熱心に読んでなかったので、詳しいことは忘れている。
生い立ちの違いがありそうだ。
クリフォード・ブラウンはデラウェア州ウィルミントン生まれ。マイルスのような金持ちの家庭ではない。しかし、裕福とは言えないが、彼の家庭は暖かく結束していた。彼は8人の子供たちのなかの5人の男兄弟の末だが、彼がいじめられたりしないように兄たちはいつも弟をかばった。
デラウェア州の共和党政府は黒人の差別にはできるだけ加担しないような政策をとったらしい。ウィルミントンの黒人社会は両大戦中には良いコミュニテイ意識があったようだ。家族内だけでなく黒人社会内でも民主的な空気が流れていたようだ。
高校や大学(黒人専用カレッジ)に進学しても、好きなトランペット以外の勉強にも励んだ。教師たちも親切だった。
こんななかでジャズ界にデビューして、順調に有名になり、26歳(1956年6月26日)でなくなるまで、挫折は経験していないだろう。クスリにも手を出していない。必要がなかったと思う。もし彼が何らかの形で、演奏に絡むところで差別を受けたらどうなっていたかを、マイルスの例と比べてこれから考えてみたい。
体調が優れない朝は、マイルスよりも。クリフォード・ブラウンの底抜けに明るい音を聞きたくなる。今も「The Best of Max Roach and Clifford Brown in Concert」を聴きながキーボードを叩いている。
マイルスの自叙伝にはブラウン死後の盟友マックス・ローチの落ち込みぶりとともに、ブラウンに対する賛辞がたくさん書かれている。『クリフォード・ブラウン』の本の索引を見ただけでは、マイルスの名は出てこない。本当に本文にもないのか、なければ、それはなぜかということも追求の対象になる\(^o^)/